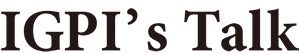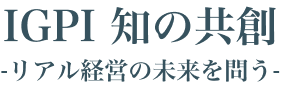私たちは、非連続な変革を志向して、
事業・企業・経済・社会のあらゆる局面に飛び込み、
時代の分岐点に重要な役割を果たします。
経営・経済の新潮流を
常に見つめ、
「探索と深化」の
両利き連鎖で
新しい時代を切り拓く
グループのユニークネス
「経営のあるべき姿」を資本主義社会に問うべく、常識を疑いながら、新機軸を創発しつづける組織構造
ユニークネス


Group Career
グループ採用情報
IGPIグループでは、時代を切り拓くために、
内在的な知的好奇心から自らの「探索と深化」を繰り返すIGPIプロフェッショナルが活躍しています。
実践の中で「真の経営人材」が繋がり、育ち合うプラットフォームであり続けることを志向しています。






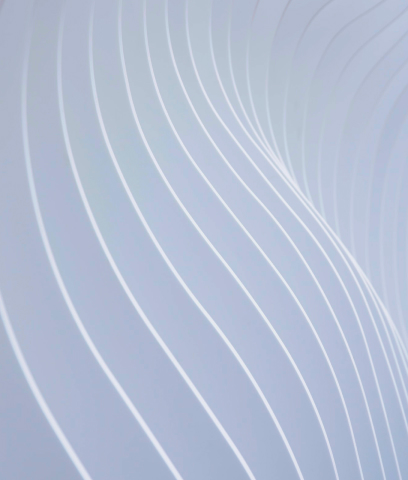

 インキュベーション
インキュベーション
 マジョリティ投資・事業経営
マジョリティ投資・事業経営
 コンサルティング
コンサルティング
 コンサルティング
コンサルティング
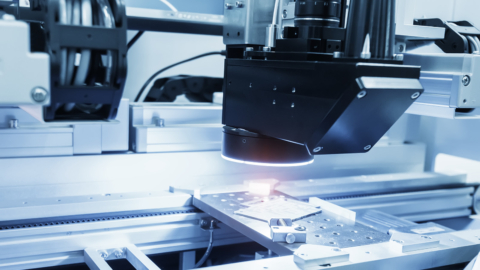 コンサルティング
コンサルティング
 マジョリティ投資・事業経営
マジョリティ投資・事業経営
 コンサルティング
コンサルティング
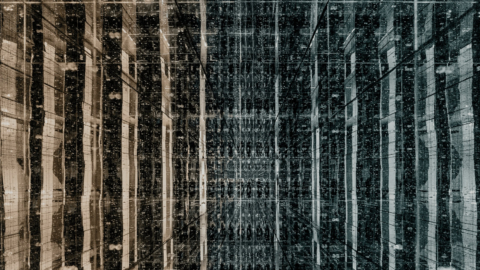 インキュベーション
インキュベーション
 コンサルティング
コンサルティング
 コンサルティング
コンサルティング
 2024/04/05 IGPI’s Talk
2024/04/05 IGPI’s Talk
 2024/03/22 IGPI’s Talk
2024/03/22 IGPI’s Talk
 2024/01/23 Top Researchers
2024/01/23 Top Researchers
 2024/01/16 Next Leaders' note
2024/01/16 Next Leaders' note
 2024/01/09 IGPI’s Talk
2024/01/09 IGPI’s Talk
 2023/12/26 Top Researchers
2023/12/26 Top Researchers
 2023/12/07 Next Leaders' note
2023/12/07 Next Leaders' note